【Legacy】僕がwillをサイドに落とす理由
2015年10月2日 レガシー
以前書いた《【legacy】ゲームに勝つためのアクセントとして》が、水面下とはいえ予想以上に反響があったのが嬉しい半分、恐縮半分くらいで何ともいえない気分になっている今日この頃です。
↓リンク
http://lolig6.diarynote.jp/201509010916096307/
さて、タイトル通りの事なのですが、僕がコレをやり始めて恐らく3.4年経ちます。最初はメイン構成が黒すぎて切れないって理由だったのですが、ゲームの流れ、展開を少し深く考えるようになった今日この頃、少し明確になったような気がした為自身の確認もかねて文に書き起こそうとしたわけです、つたない文となりますがお付き合い頂ければ幸いです。
■《will》を切るタイミングを明確に可視化できない。
最初っから答えっぽいのですが結構な率でコレが来ると思います、環境が対コンボまみれだったら話は別なのですが、《dig》が禁止となり少しビートも復権する可能性がある今いま一度確認する必要があると思います。
・《will》でできる事は、他のカードで代用が効く場合が多い。
例えば相手の《タルモゴイフ/Tarmogoyf》に対し切る、切らないの話ですが自身が除去を握っていればわざわざ切る必要はありません、また手札になかったとしてもドロソを握っていてソレを代価に弾くか、それとも探すかという選択肢を迫られるわけです。
後者の場合、体感ですが選択肢として探すプレイヤーが多いともいます、使う側もハンドを1枚失うリスクを承知してる訳ですから当然っちゃ当然かと思います。ちなみにこの文だけで正解はありません、結果が全てでもう少し盤面やハンドに触れられていれば話は別ですが、またそれは別のお話です。
■切りにいく《will》と切らされる《will》
さてここは【Legacy】青使いの永遠のテーマとなる部分です、ちょっと本腰入れていきましょう。一応ですが前者が強ムーブで後者が弱ムーブだと思ってください(対コンボの場合は違う事もあります)。
・切りに行く《will》は誰が見ても可視化できている。
分かりやすくいえば[SnT]の《will》です、これは誰が見ても強いですよね。だって通せば勝ちだから。そして[ANT]に対する《will》etc…
一撃死を防ぐ、強要する場合は上でも上げたとおり容易いものです、では本題の切らされる側について考えていきます。
・切らされる《will》は可視化できず、使われる側が可視化できている。
切った側はモヤっとする一瞬です、何故ならこの切ったハンド一枚(有効牌)が大きくゲームを左右するからです。大体クロック、ドロソ、カウンターですがどれもゲーム展開を引き寄せるには重要なカードです。果たして相手は本当に痛手を負ったのか、それとも自信が勝手に痛手を負っているだけなのか?ここが大事になってくると思います。
ここでタイトルの答えが出ますが、僕はこの切らされる展開にもやっとしたものを感じ勝つ感覚が鈍く、負けた感覚が強く残ります。
「あぁ、あの切らされる《will》がほんと強かった」という感想は(メインで試した時)対コンボ以外持った事がなく、一方的なゲームだけです。ワンサイドゲーは勝つ感覚を掴むにはいいですが、勝ちきるために本当に大事な事は学べません。「大事なのは下から真ん中に戻す力、そしてそこから波に乗るの2工程。」
僕はこの工程を《will》ではなく他のカードで補おうとしました。その為どんどんジャンク色が強くなり、色もよりこく多彩になりました。
ある種僕は環境にあったメタカード、狂カードの多彩な組み合わせに甘えているだけなのかもしれません。しかしこの甘えれる選択肢こそがメイン、サイドをより鋭利なものにするのは間違いありませんし、僕の持ち味はここの特化だと思っています。
※(《will》持ちはどんなデッキにも50%は芽があるという事)
さて、僕が思う《will》について書きつつって見ましたが如何だったでしょうか?人それぞれ色んな感想を持つと思いますがこの一枚を見つめなおすきっかけ位にはなれればいいかと思います。
願わくば少しでも賛同していただき、色んなカードの組み合わせを試す、考える、そんなプレイヤーが増えてくれればと願うばかりです。そしたらもっとデッキやカードの種類が環境に増えていくのではないでしょうか。
↓リンク
http://lolig6.diarynote.jp/201509010916096307/
さて、タイトル通りの事なのですが、僕がコレをやり始めて恐らく3.4年経ちます。最初はメイン構成が黒すぎて切れないって理由だったのですが、ゲームの流れ、展開を少し深く考えるようになった今日この頃、少し明確になったような気がした為自身の確認もかねて文に書き起こそうとしたわけです、つたない文となりますがお付き合い頂ければ幸いです。
■《will》を切るタイミングを明確に可視化できない。
最初っから答えっぽいのですが結構な率でコレが来ると思います、環境が対コンボまみれだったら話は別なのですが、《dig》が禁止となり少しビートも復権する可能性がある今いま一度確認する必要があると思います。
・《will》でできる事は、他のカードで代用が効く場合が多い。
例えば相手の《タルモゴイフ/Tarmogoyf》に対し切る、切らないの話ですが自身が除去を握っていればわざわざ切る必要はありません、また手札になかったとしてもドロソを握っていてソレを代価に弾くか、それとも探すかという選択肢を迫られるわけです。
後者の場合、体感ですが選択肢として探すプレイヤーが多いともいます、使う側もハンドを1枚失うリスクを承知してる訳ですから当然っちゃ当然かと思います。ちなみにこの文だけで正解はありません、結果が全てでもう少し盤面やハンドに触れられていれば話は別ですが、またそれは別のお話です。
■切りにいく《will》と切らされる《will》
さてここは【Legacy】青使いの永遠のテーマとなる部分です、ちょっと本腰入れていきましょう。一応ですが前者が強ムーブで後者が弱ムーブだと思ってください(対コンボの場合は違う事もあります)。
・切りに行く《will》は誰が見ても可視化できている。
分かりやすくいえば[SnT]の《will》です、これは誰が見ても強いですよね。だって通せば勝ちだから。そして[ANT]に対する《will》etc…
一撃死を防ぐ、強要する場合は上でも上げたとおり容易いものです、では本題の切らされる側について考えていきます。
・切らされる《will》は可視化できず、使われる側が可視化できている。
切った側はモヤっとする一瞬です、何故ならこの切ったハンド一枚(有効牌)が大きくゲームを左右するからです。大体クロック、ドロソ、カウンターですがどれもゲーム展開を引き寄せるには重要なカードです。果たして相手は本当に痛手を負ったのか、それとも自信が勝手に痛手を負っているだけなのか?ここが大事になってくると思います。
ここでタイトルの答えが出ますが、僕はこの切らされる展開にもやっとしたものを感じ勝つ感覚が鈍く、負けた感覚が強く残ります。
「あぁ、あの切らされる《will》がほんと強かった」という感想は(メインで試した時)対コンボ以外持った事がなく、一方的なゲームだけです。ワンサイドゲーは勝つ感覚を掴むにはいいですが、勝ちきるために本当に大事な事は学べません。「大事なのは下から真ん中に戻す力、そしてそこから波に乗るの2工程。」
僕はこの工程を《will》ではなく他のカードで補おうとしました。その為どんどんジャンク色が強くなり、色もよりこく多彩になりました。
ある種僕は環境にあったメタカード、狂カードの多彩な組み合わせに甘えているだけなのかもしれません。しかしこの甘えれる選択肢こそがメイン、サイドをより鋭利なものにするのは間違いありませんし、僕の持ち味はここの特化だと思っています。
※(《will》持ちはどんなデッキにも50%は芽があるという事)
さて、僕が思う《will》について書きつつって見ましたが如何だったでしょうか?人それぞれ色んな感想を持つと思いますがこの一枚を見つめなおすきっかけ位にはなれればいいかと思います。
願わくば少しでも賛同していただき、色んなカードの組み合わせを試す、考える、そんなプレイヤーが増えてくれればと願うばかりです。そしたらもっとデッキやカードの種類が環境に増えていくのではないでしょうか。
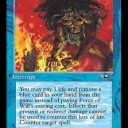

コメント